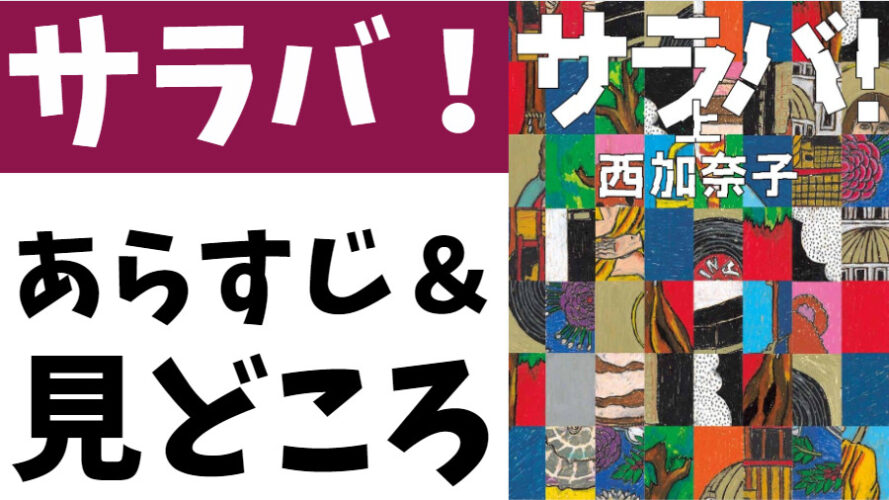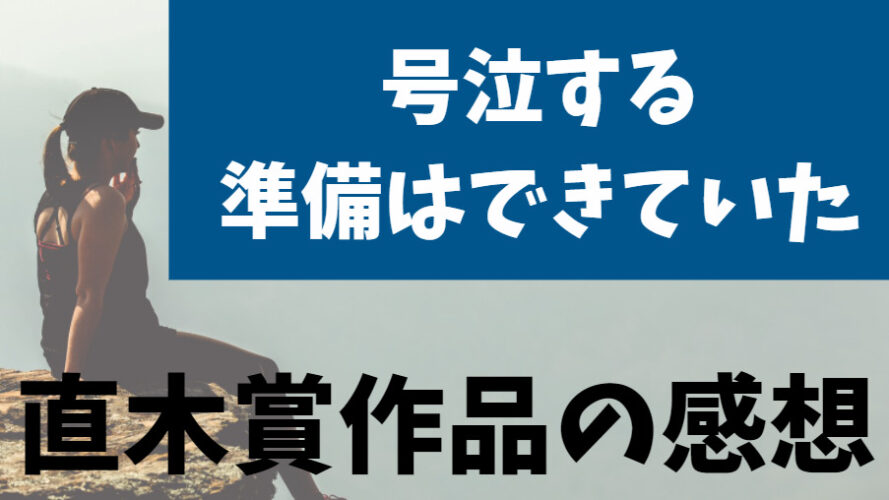2020年7月、樺太アイヌの「こころの戦い」を目の当たりにして、泣きました。
162回直木賞受賞作品、というだけで手に取った「熱源」は日本やロシアに翻弄されたサハリンの様子を、実在の人物を主人公に描いています。
わりと読みやすくスルスルっと進められる面白さはあるものの、人物の名前が「ヤヨマネクフ」「クルニコワ」「ブロニスワフ・ピウスツキ」とか、とても覚えにくく、そこが最後まで難問として引っ掛かります…。
サハリン(樺太)とロシアとポーランドの名前は、日本人にとって発音が難しいんですよね^^;
今回は熱源のあらすじと、感想。時代背景の解説もあわせてまとめてみました。
↑画像タップでアマゾンkindleで読めます!
アマゾンkindleは、月額980円で12万冊が読み放題です!
\今なら30日間無料/
- 面白さ:
 (4.5 / 5)
(4.5 / 5) - 読みやすさ:
 (4 / 5)
(4 / 5) - 導入の引きこみ:
 (5 / 5)
(5 / 5) - 読んだ後の満足感:
 (5 / 5)
(5 / 5) - 読むのにかかった時間:120分
熱源の登場人物一覧

- ヤヨマネクフ(山辺安之助)
…樺太アイヌで実在の人物。アイヌの教育に力を注ぎ、文明に飲み込まれる「アイヌ」を何とか生かし続けたいと願い続ける。 - シシラトカ
…ヤヨマネクフの親友で幼馴染。軽薄で軽率に書かれているが、ヤヨマネクフとともに南極探検隊に加わるなど、歴史上の人物。 - 太郎治
…アイヌと和人(日本人)の混血で、教師としてアイヌに日本語や文明を教え続ける。 - キサラスイ
…ヤヨマネクフの恋人で、五弦琴の名手。 - チコビロー
…ヤヨマネクフの育ての兄であり、父親的存在。 - バフンケ
…樺太アイ村の頭領で、実在の人物。 - イペカラ
…バフンケの養女で五弦琴の名手で、ロシア侵攻時に命の危機になる。 - チョフサンマ
…バフンケの姪で、ブロニスワフと親しくなる。実在の人物。 - ブロニスワフ・ピウスツキ
…ロシアによって滅ぼされたポーランド復興を胸に抱きながらも、政治犯としてサハリンに流刑となり、その地でアイヌやギリヤークという先住民に心を奪われ、アイヌの女性と結婚。生涯をアイヌの研究と、ポーランドの独立運動に捧げるが、運動の闇に飲み込まれる。 - ヨゼフ・ピウスツキ
…1918年、ロシアから独立した初代ポーランド大統領で実在の人物。「熱源」の中で焦点が当たることはほとんどなく、大統領になることも描かれていないが、ブロニスワフの弟として登場する。 - コヴァルスキ
…ロシアの民俗学者で、アイヌの調査にやってくる。 - 金田一京助
…アイヌの研究に人生をささげた東京帝大の助教授で、実在の人物。(金田一少年のおじいちゃんの金田一耕助とは別人) - クルニコワ
…ロシア軍の伍長で、第二次世界大戦の終わりごろに、樺太侵略軍としてやってくる。
熱源の舞台

熱源はおもに樺太(サハリン)を舞台に書かれていますが、主人公の1人のブロニスワフが世界を股に駆け回るので、ロシアとポーランド国境、バルト三国あたりがちょいちょい登場します。
熱源の時代
時代は1867年ごろから1945年の、第二次世界大戦の終戦時までが描かれています。
- 1867年…明治維新の大政奉還(江戸幕府消滅)
- 1867年…坂本龍馬の没年
- 1904年~5年…日露戦争
- 1912年…白瀬のぶが南極大陸に上陸する
- 1914年…大隈重信が2回目の内閣総理大臣となる(大隈さん、熱源に登場します)
- 1914年~18年…第一次世界大戦
- 1912年~1926年…大正時代
- 1931年…満州事変
- 1939年~45年…第二次世界大戦
このように、熱源で描かれている時代には、日本は戦争だらけ…。軍事国家として破滅の道を進んでいるさなかでした。日本のどこに住んでいても、激動の人生と思われるこの時代…樺太のアイヌは、ロシアと日本の両側からの侵略で、アイヌの生き方を奪われ続けました。
登場する民族

- アイヌ
…樺太南部から、北海道、本州の南部にまたがって生きていた民族。狩猟民族であり、サバイバルスキルが卓越しているが、日本やロシアの領土拡張にともない、日本人やロシア人として編入されてしまった。 - オロッコ
…樺太東部に住んでいたサハリンの民族の一つ。 - ギリヤーク
…サハリンに住んでいたロシアの先住民でニグブン(人)と呼ばれていた。 - 和人
…明治政府による「日本人」の総称。 - ポーランド人
- ロシア人
熱源のあらすじ

群像劇のようでありながら、熱源はヤヨマネクフとブロニスワフの2人を主人公としています。
2人とも名前が呼びにくすぎる…でも仕方ない。実在の人物ですから!
ヤヨマネクフの物語
北海道に移住したヤヨマネクフは、養父とともに和人の中で生活するが、暮らしは厳しくコレラの流行などによって、北海道アイヌの数は激減した…。
大切な人の多くを失ったヤヨマネクフは、10数人の生き残りとともに、生まれ故郷の樺太に戻る。
だが、故郷で待っていたのは、文明を持たないアイヌが、文明を縦に人間の優劣を突きつけてくる、日本とロシアからの略奪されつくす姿だった…。
度々の戦争や侵略で死に続ける人々。
言語や法律による取り締まりのなか、何とか「アイヌ」を存続させ、「アイヌ」に意味を持たせようと、生涯をささげていく。
ブロニスワフ・ピウスツキの物語

一方で、祖国ポーランドをロシアに支配され、言語を奪われたブロニスワフは、サンクトペテルブルグの大学時代に、学生運動に参加して政治犯とされ、樺太に流刑を課せられた。
囚人として仕事をする中で、現地に住むギリヤークの狩猟採集の生活の美しさに魅せられ、行動を共にするようになる。
やがてロシアと日本という2つの領土拡張に飲み込まれそうになるアイヌに心を奪われ、その美しい生き方に淘汰されたいと願うようになる。
しかし弟のヨゼフ・ピウスツキはポーランドの独立のために激しい政治運動をしており、やがて故郷のその運動に巻き込まれていく。
ヤヨマネクフとブロニスワフの出会い
ロシアの民族研究学者の依頼で、アイヌの研究をしているブロニスワフと、樺太のアイ村付近で過ごすヤヨマネクフ。
ヤヨマネクフは妻をコレラでなくして以来、堅物っぽくなっているが、ともにアイヌの「滅び」を阻止するために、文明に関する教育に力を注ぐ。
ある日ブロニスワフがアイヌの琴の音を録音していると、ヤヨマネクフが録音機に語り始める。
「我々は滅びゆく民と言われているが、これを聞いている未来の時代のどこかでも、私たちの子孫は変わらず…あるいは変わりながらも生きています。」と未来へのメッセージを送った。
その後世界は第二次世界大戦に突入し、2人は遠い地でお互いの消息を知ることになる。
「熱源」とはなに?

タイトルの「熱源」という言葉が、不意に出てきて涙を誘います。
ヤヨマネクフにとっての「熱源」とは
和人から「犬め」と言われた幼少期に、胸の中に感じた「熱」を、ヤヨマネクフは生涯をかけて問いただし続ける…。この熱さは何なのか。怒りか?憎しみか?反骨精神か?誇りが焼かれているのか?
…違いました。
ヤヨマネクフにとっての「熱の源」は人だった。悲しい別れをたくさん経験し、その人たちの記憶に突き動かされて生きてきた。
生きるための熱の源は「人」でアイヌとは「人」という意味。偉大なことをしなくても、世界に「アイヌは偉大だ」と見直されなくても、ただ生きているだけで、それでいいのだと、ヤヨマネクフは、自分の熱源を知ったのです。
ブロニスワフにとっての熱源とは
ブロニスワフにとっての熱源とは「故郷」のこと。
第一の熱源は、子どもの頃失われたポーランドの大地。第二の熱源は、サハリンの妻子の元…。
北海道には今も、ブロニスワフの子孫が生きています。受け継がれるブロニスワフとアイヌの血は、現代でもブロニスワフの「熱源」に生き続けているんです。
大隈重信にとっての熱源とは

作中に出てくる大隈さんは「熱源」という言葉は使わないが、弱肉強食で列強の諸国に食われないために、弱いものを食って強者となることを熱意をもって語り掛けます。
それに対し、ブロニスワフは「弱肉強食の強者と闘うのではなく、【弱肉強食】という摂理と戦う」と応じる。
ヤヨマネクフは「どんな世界でも適応して生きていく。俺たちはアイヌだから。アイヌには【人】という意味があるから。」と応じる。
激動の時代に大波に飲まれず、自分の真理を見つけ出した2人の男たちが、大隈総理をうならせた名場面です。
クルニコワにとっての熱源とは
ロシアの伍長、クルニコワは、終戦のその時に樺太でアイヌと不思議な出会いを果たし、その出会いと樺太の地を「熱い」と感じる。戦争の持つ不条理をなめてきたクルニコワは、ずーっと冷たい世界を生きているかのように書かれています。
けど、クライマックスで彼女は初めて熱を感じ、「熱い」と口に出し、それを「変わった産声だ」と自嘲します。物語の最後に、クルニコワは初めて「熱」を帯びるんです。
「熱源」の感想(私の)
見えない敵

ヤヨマネクフは子どもの頃から、見えない敵を不気味に思っていました。「自分たち(アイヌ)が何に飲み込まれようとしているのかわからない」と話しています。
本を読んでいても、目に見える暴力描写がほとんど出てこず、アイヌはただ住む場所を追われ、その先で細々と和人の文明ルールに従いながら生き続けます。
字や言葉の壁により理不尽な立ち退きを言われても、ただ追われるのみ…。抵抗という抵抗がほぼ描かれず、アイヌは和人やロシアのなすがままにされているように感じます。
アイヌがもともと持っていた狩猟採集や物々交換の民族性は無視され、お金や法律がじわじわと入り込んできます。その代わりにもたらされる「文明の恩恵」に価値を見出せない…。和人のもたらす暮らしはじわじわと見えない糸で首を絞めるように、アイヌを「アイヌ」でなくしていくような、不気味な描写がされています。
南極探検の犬ぞり隊

史実の白瀬のぶという男が、南極点を目指して寄付を募り、南極探検に乗り出すシーンが出てきます。そこに同行する「犬ぞり」部隊のことを聞いて、まず「タロとジロ?」と思うのだけど、タロとジロは1957年の南極探検にいた犬なので、時代はもっと後でした。
樺太のアイヌやギリヤークたちが犬ぞりを好んで移動手段とすることから、南極探検の犬たちは概ね樺太付近で募集されたんですよね。
この時は残念ながら南極点には達しなかったけど、歴史上の人物や出来事がフィクションの小説に出てくると、興奮しますね笑。
クロニコワの存在感
熱源の冒頭と、ラストのちょっとだけに出てくるロシアの伍長のクロニコワ。ほんのわずかな登場シーンなのにもかかわらず、彼女の胸に湧き出る「見えない敵との戦いにもやもやしているところ」と「熱」に、新たな熱源を感じられます。
最初にちょっと出ただけなのに、最後に登場したときに「やっと出てきた!」と待ってましたって気分になるほど存在感は抜群でした。
しかも、ちょうどこないだ「戦争は女の顔をしていない」という本を読んだので、ロシア軍に当たり前のように存在した「女の兵士」に気持ちがざわつきました。
「戦争は女の顔をしていない」では、彼女たちには男とは違う戦いがあり、味わう苦しみも想像できないほどでした。(もちろん戦争は男の兵士に与える影響も大きく、男女格差を言いたいのではありません。)
ただ、私もジムや体を動かすことが好きなので、女もOKの徴兵制度があれば、国や時代によっては参戦していたのかも、とリアルに想像してしまいました。
それだけに、クルニコワの在り方や気持ちは、作中で一番身近に感じられました。同じように思う女性も多いと思います。
↑画像タップでアマゾンkindleで読めます♪
こちらの原作本も面白くはあるけど、重い内容の上に淡々と描かれているので原作は退屈に感じるかも。原作を元にした漫画バージョンがあるので、サラッと見たい方はこちらがおすすめです。
アマゾンkindleは、月額980円で12万冊が読み放題です!
\今なら30日間無料/
アイヌを知れるおすすめマンガ
わたしがアイヌに興味を持ったのは「ゴールデンカムイ」とか手塚治虫の「シュマリ」とか…。北海道の先住民で、今は完全に日本とロシアに滅ぼされてしまった民族、と認識していました。
この漫画たちは2つとも、和人やロシアに駆逐されるがままの弱者としてのアイヌを描いています。熱源とは違った角度からのアイヌについて知れる作品です。
>>勉強になる「学習まんが26選!」では、大人でも学べるマンガを紹介しています。
さいごに
激動の時代では、アイヌでなくとも人々は正体不明の「熱」を感じて、苦悩していたのだろうな、と想像してしまった作品でした。
162回直木賞受賞作品、本当に面白かったです!
是非、手に取って読んでいただければと思います。
↑画像タップでアマゾンkindleで読めます!
アマゾンkindleは月額980円(初回30日無料!)で12万冊が読み放題の一番お得と言っていい電子書籍アプリです!
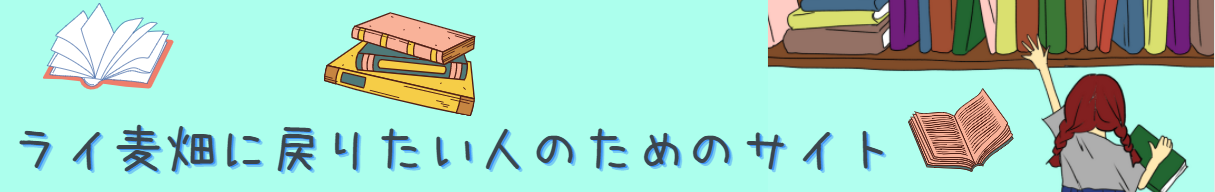

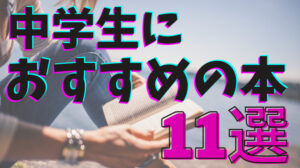
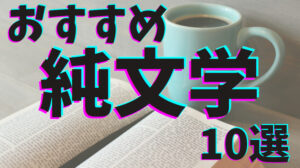
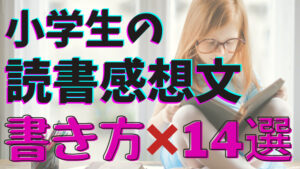

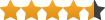 (4.5 / 5)
(4.5 / 5)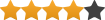 (4 / 5)
(4 / 5)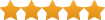 (5 / 5)
(5 / 5)